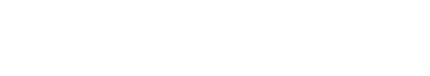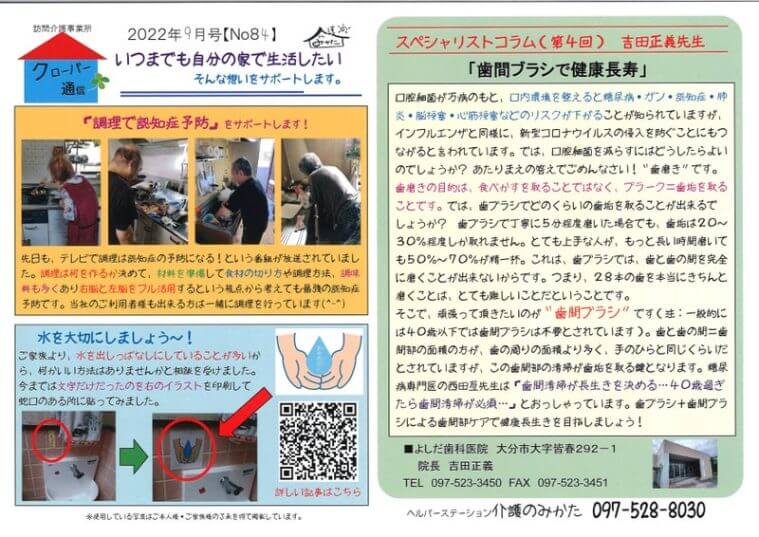人を集める”のではなく、“人が集まる場所”をつくる”
大分ホームヘルパー訪問介護のみかた介護支援コンサルタントの秦です。
今回は介護事業所が抱える人材不足について書こうと思います。
介護業界の人材不足は深刻だ。
どの事業所も「採用が難しい」、「辞めてしまう」と声を上げている。
しかし、そもそも人材不足とは「人がいない」というより、「人が集まりたくなる理由がない」状態を指すのではないだろうか。
どれだけ求人広告を出しても、どれだけ面接を繰り返しても、「ここで働きたい」と心から思える施設でなければ、長く続かない。
だからこそ、介護の人材問題は“採用活動”ではなく“魅力づくり”の問題として考える必要がある。
■待遇改善だけでは人は定着しない

介護の現場では、給与や福利厚生を改善すれば人が集まると考えがちだ。
もちろん待遇は大切だが、それだけで人が定着することはない。
なぜなら、より条件の良い職場が現れれば、簡単に移ってしまうからだ。
つまり、「給料で集めた人材」は、給料で去っていく。
大切なのは、「ここで働く意味がある」と感じられる環境をつくること。
お金ではなく、誇りや納得感で人が動く職場こそが、真に強い組織をつくる。
■現場の“困りごと”をビジネスの種にする

人材不足を嘆く前に、まず現場の声に耳を澄ませてほしい。
スタッフの「困っていること」、「不満に感じていること」の中には、必ず組織を強くするヒントが隠れている。
たとえば、「シフトが急で生活のリズムが崩れる」、「夜勤の負担が偏る」、「新人教育の時間が取れない」。
これらを“問題”として処理するのではなく、“改善のチャンス”として捉え直すことが重要だ。
仕組みを整えれば、それは単なる働きやすさではなく、“働きたい場所”に変わる。
現場の困りごとは、実は職場を魅力的にするための贈り物でもある。
■業界の常識を疑う
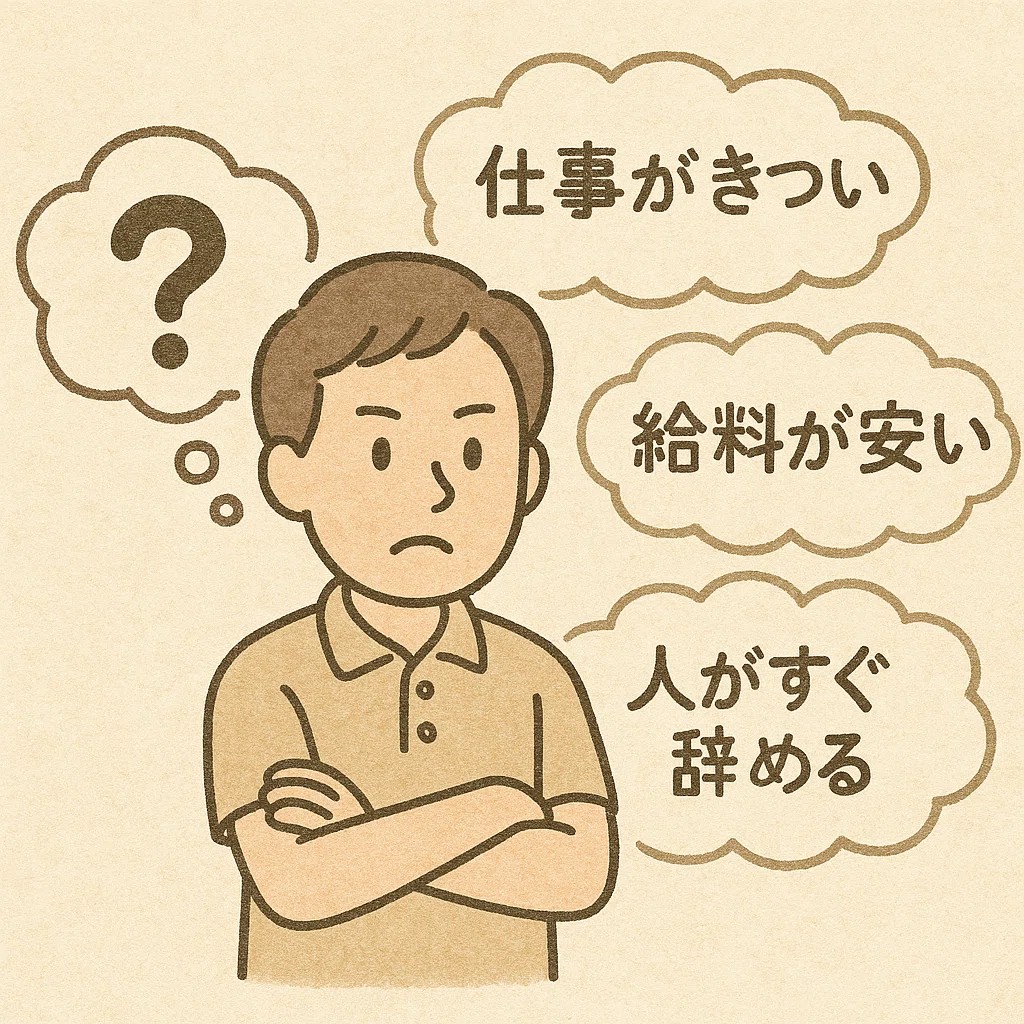
「介護の仕事はきつい」、「給料が安い」、「人がすぐ辞める」、こうした言葉を“当たり前”と思っていないだろうか。
この思い込みこそが、介護の未来を閉ざしている。
常識を疑えば、新しい発想が生まれる。
たとえば、夜勤を「孤独な時間」ではなく「利用者と静かに向き合える貴重な時間」として再定義する。
あるいは、入居者の人生の物語をスタッフ全員で共有し、“作業”ではなく“人と生きる仕事”に変えていく。
言葉の意味を変えれば、働く人の意識も変わる。意識が変われば、離職率は下がる。
■理念が人を集め、仕組みが人を育てる
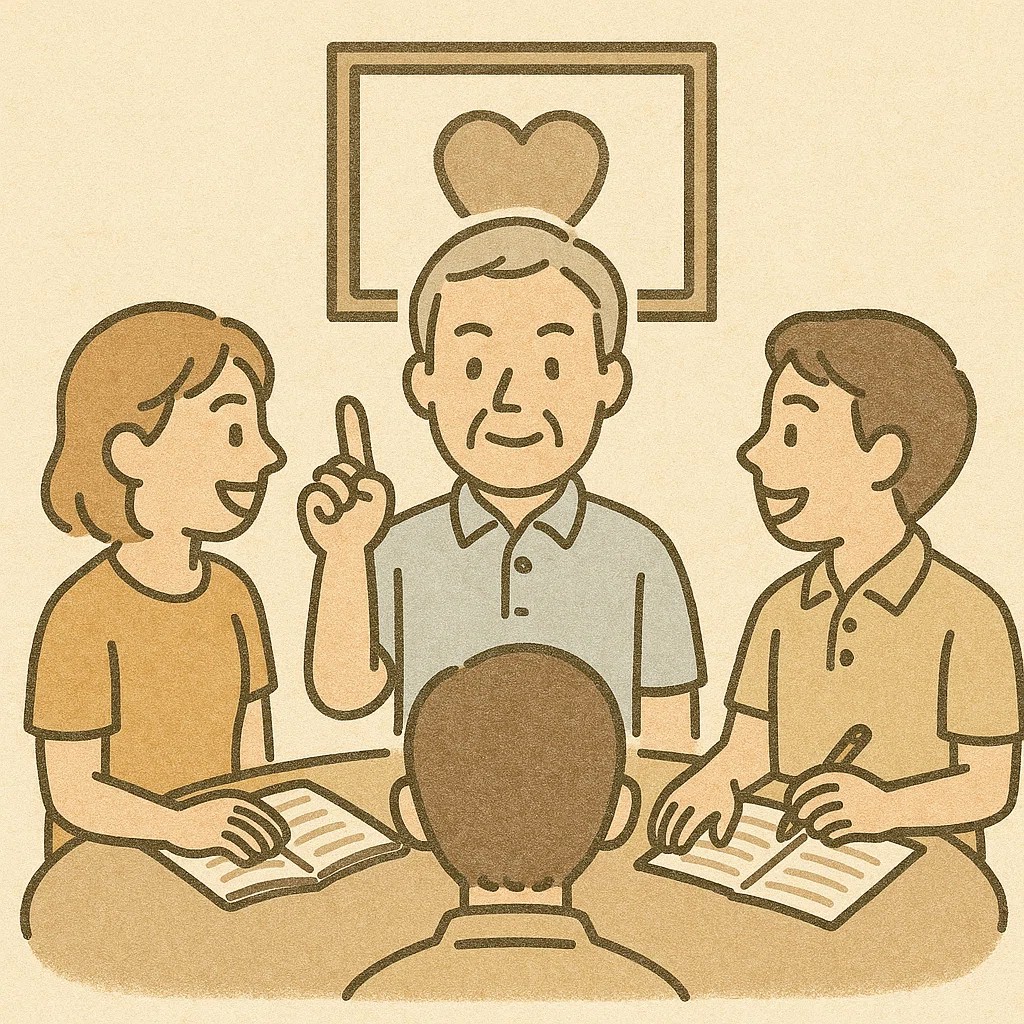
どんなに制度やマニュアルを整えても、理念がなければ形だけの組織になってしまう。
「なぜ介護をするのか」、「誰のための介護なのか」、この問いに答えられる職場だけが、長く人を惹きつける。
理念はスローガンではない。
トップが心から信じ、行動で示すものだ。
そして、その理念を日々の仕組みに落とし込むことが何より大切だ。
たとえば、スタッフ同士で「今日いちばん心が動いた瞬間」を共有する時間を設けるだけでも、現場の空気は変わる。
■介護の未来を変えるのは“採用力”ではなく“魅力”

本当の意味での人材不足とは、「働く人がいない」のではなく、「働きたいと思える職場が少ない」ということだ。
だからこそ、求められるのは“人を増やす”努力ではなく、“魅力を増やす”努力である。
介護の仕事を誇りとする人が増えれば、この業界の価値そのものが上がる。
人材が集まる事業所とは、求人を出さなくても噂が人を呼ぶ事業所だ。
それは、誰かに選ばれるためではなく、「ここで働くことが幸せ」と思える文化を持っている場所である。
人を採るのではなく、人が集まる。
この逆転の発想こそが、介護の未来を変える最初の一歩になる。
セミナーや講演の依頼はこちら
https://clover-m.co.jp/seminar/