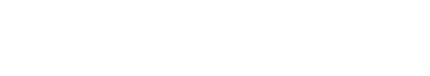大分ホームヘルパー訪問介護のみかた、介護支援コンサルタントの秦です。
大分ホームヘルパー訪問介護のみかた、介護支援コンサルタントの秦です。
今回はリーダーについての話です。
ある介護事業所での話
現場のリーダーが、スタッフルームの隅で冷めたコーヒーを見つめていた。
「人が足りません。新人が続かない。現場は毎日ギリギリです。何をどう改善すればいいのか分からないんです。」
そうつぶやきながら、彼は上司に提出する報告書の締切を思い出し、立ち上がった。
この事業所では、毎週「リーダー会議」が開かれている。
だが話し合われるのは、「シフト調整」「苦情対応」「新人教育」など、目の前の問題をどう処理するかということばかり。
「なぜこの事業所が存在するのか」
「どんな介護を提供したいのか」
といった根本的な議題は、一度も出てこない。

働く人たちは真面目で優しい。
けれど、毎日の業務に追われるうちに、いつの間にか「こなすこと」が仕事の目的になっていた。
そして、気がつけば“考えないリーダー”ばかりが増えていった。
この構図は、介護の現場では決して珍しくない。
「リーダーを増やすための研修」を繰り返しても、なぜか自分で考えて動ける人が生まれない。
それは、リーダーを育てる以前に、「目的を共有する文化」が育っていないからだ。
「改善」だけでは、リーダーは育たない
多くの事業所では、業務改善や離職防止、チーム強化といった取り組みが行われている。
だが、それらがいつの間にか「やることが目的」のなってしまうことが多い。
「報告を徹底しよう」
「ミスを減らそう」
「効率化を進めよう」
それ自体は悪くない。
けれど、“なぜそれをやるのか”という根拠となる目的が欠けていれば、改善は“作業”になる。
そこに「人の心」は動かない。
リーダーに求められるのは、マニュアルを覚えることではなく、目的を行動に翻訳する力だ。
たとえば「利用者の尊厳を守る」と掲げるなら、どのような場面で、どんな言葉や態度がそれを実現しているのかを具体的に語れなければならない。
目的は立てるものではなく、現場の判断の“軸”である必要がある。
目的が曖昧なまま改善を進めると、スタッフは「上から言われた通りに動く人」になる。
目的が明確なら、「なぜそれをするのか」を自分で考えるようになる。
リーダーとは、その“考える文化”を現場に根づかせる存在だ。
「考える場」がなければ、人は考えない

リーダーを育てるうえで最も大切なのは、「考える場」を仕組みとして持つことだ。
多くの事業所では、会議といえば「報・連・相」や「ヒヤリハットの共有」が中心になりがちだ。
それらはもちろん必要だが、それだけではリーダーは育たない。
必要なのは、“目的をもとに語る場”だ。
たとえば、こんな問いから始めてみる。
「この一週間で、利用者が笑顔になった瞬間はどんな時だったか?」
「自分たちの介護で誇りを感じたのはどんな場面だったか?」
「この事業所にしかできないことは何か?」
こうした対話は、単なる振り返りではない。
目的を日常の中に引き戻す行為であり、スタッフ一人ひとりが「自分たちは何者か」を考える時間になる。
その積み重ねが、リーダーの思考をつくる。
リーダーは「指示を出す人」ではなく、「問いを投げる人」だ。
問いのない組織に、考える人は生まれない。
「無理な依頼」を学びに変える

介護の現場では、家族や利用者からときに“無理なお願い”が持ち込まれることがある。
多くの事業所では、無理なお願いを「困りごと」として処理する。
だが実は、ここにこそリーダーを育てる種がある。
その「困りごと」は、利用者や家族の“真の願い”の裏返しだ。
それ自体が、“この人なら信頼できる”という期待の表れかもしれない。
リーダーは、そうした要望を単なるトラブルとして片づけるのではなく、「なぜこの依頼が生まれたのか」を考える必要がある。
その背景を理解し、再発防止ではなく「仕組み化」につなげていく。
それが、現場を“反応する組織”から“創造する組織”へと変える第一歩になる。
「リーダー=管理職」という誤解

多くの事業所で、リーダーという言葉は「中間管理職」と同義に使われている。
だが本来のリーダーとは、肩書きではなく“姿勢”である。
それは、「なぜ?」と問い続ける人のことだ。
「なぜこのケアが必要なのか?」
「なぜこの順番で行うのか?」
「なぜ私たちはこの事業所にいるのか?」
この問いを繰り返すうちに、他人事だった仕事が自分事に変わる。
自分で考えるようになったスタッフが増えれば、指示命令に頼らなくても現場は回る。
リーダーを増やすとは、肩書きを増やすことではなく、思考する人を増やすことなのだ。
言葉で目的を生かす
目的は、ただ立てるだけでは力を持たない。
「この世界は言葉でできている」と言われるように、目的も言葉にして初めて現実になる。
事業所の目的を、スタッフ一人ひとりが自分の言葉で語れるようになること。
「当社の目的は〇〇〇〇です!」と言うなら、それを“どう行動で示すのか”を自分の言葉で言えるようにする。
その瞬間、目的はただの言葉から現場へと降りてくる。
目的を言葉にし、行動に変える人がリーダーであり、
その連鎖が始まった時、事業所全体に「やりがいの空気」が流れ始める。
「思考」と「行動」をつなぐ人

リーダーとは、思うだけでも、動くだけでも足りない。
考え抜いたうえで動く人である。
そして、動いた結果をまた考え、次の行動へとつなげる。
それが、事業所を強くする循環だ。
「思う力」と「行う力」が結びついたとき、人は初めて自分の仕事に誇りを持つ。
その誇りが、他者への敬意を生み、介護の質を高めていく。
まとめ
介護事業所でリーダーが育たない理由は、能力不足ではない。
目的を語る時間がなく、考える文化が育っていないからだ。
「目的を中心にした対話の場をつくる」
「無理な依頼を学びに変える」
「問いを投げかけるリーダーを育てる」
これらを続けることで、やがて事業所には“唯一無二の思想”が根づく。
それはどんなマニュアルにも書かれていないが、どんな経営手法よりも強い。
介護の仕事は、目的によって初めて“力”を持つ。
目的を信じ、考え、行動し続ける人。
そのようなリーダーが増えるほど、介護は社会の希望になる。
私はそう思います。
当社ホームページはこちら
https://clover-m.co.jp/